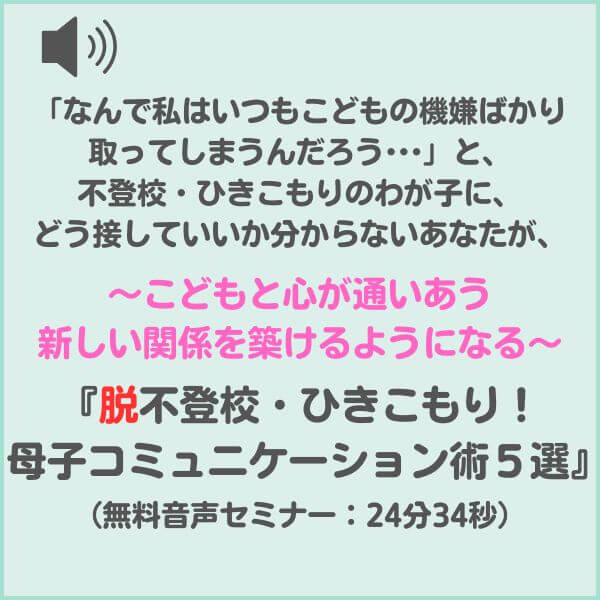ひきこもりの子の自己肯定感を支える親の心|「生きているだけでいい」

こんにちは。
不登校・ひきこもりの母親専門『チェンジングカウンセラーⓇ』の平井いずみです。
ひきこもりの子がなかなか動けず、どう関わればいいのか分からない・・・
そんな不安を抱えるあなたへ。
「この子は、このままで大丈夫なんだろうか・・・」
「このまま何もしないで、将来どうなるの?」
ひきこもりの子を見守る毎日って、親にとっては自分の中で、答えのない数え切れないほどの『葛藤』と戦っているような日々です。
実は、まさにこれは、息子の不登校・ひきこもりで悩んでいた頃の私自身の状態。
そして、そんな葛藤の裏には「私がこの子をこんな状態にしちゃったんだ・・・」という自責の念も隠れていて。
朝、部屋のドアの前で声をかけるのを一瞬ためらう。
勇気を出して「おはよう」と声をかけても返事はなく、部屋の中から聞こえてくるチャットを楽しむ声だけが息子の“生存確認”になっている。
そんな日々の中で、私の心は少しずつ疲弊していって・・・
「いつまでこんなことをしているんだろう」
「私の育て方が悪かったんだ」
「このままでは、この子の人生が終わってしまうのでは・・・」
こうして悩み続けていた当時の私のように、今のあなたも苦しんでいるのかも知れませんね。
そして、あなたがこの記事を読んでいるということは、
「このままではいけない」
「この子にもっと寄り添いたい」
そんな想いがあるからではないでしょうか。
あなたのその気持ちこそが、ひきこもりの子の自己肯定感を支える土台です。
そこで今日は、ひきこもりのこどもの自己肯定感を支えるために、親ができることを一緒に考えていきましょう。
あなたの心が少しでも軽くなりますように・・・
目次
ひきこもりの子が自己肯定感を失ってしまう理由

ひきこもりのこどもは、よく「甘えている」「逃げている」と言われがちですが、実際には「自分なんて生きている価値がない」と、感じていることが少なくありません。
それは、ひきこもりの子の多くが、学校や社会の中で失敗や挫折を経験していて、表面上では見えない深い傷や痛みがあり、自分を強く否定しているからです。
そのため、
「勉強もしていない」
「友達もいない」
「このままじゃ、社会に出られる気がしない」
こうしたマイナスの思いが、何度も心の中でループしてしまう。
そして、「自分は生きていていいのだろうか」という、強い自己否定まで抱えてしまうこともあります。
この「自己肯定感の低下」こそが、ひきこもり状態を長引かせる大きな要因のひとつ。
私たち親だって、もしこんな状況にいたとしたら、外に出ること、誰かと関わることが怖くなって、心のドアを閉めちゃったりしますよね。
だからそんな時には、親がいくら励まそうとしても、その言葉自体が本人にとっては重くのしかかり、「プレッシャー」となって届いてしまうことがあるのです。
つまり・・・ひきこもりのこどもが動けないのは、甘えでも逃げでもなく、“心のエネルギーが枯れている状態”なのだと、視点を変えて捉えてみてくださいね。
※今の日本の現実である子どもの自己肯定感の低さと、不登校・ひきこもりとの関係を詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ^^
【関連記事】子どもの不登校・ひきこもりと自己肯定感の関連性
親の励ましが、ひきこもりの子の自己肯定感を下げてしまう理由

それでは、どうして親の励ましが、ひきこもりのこどもにとってプレッシャーになって、自己肯定感を下げてしまうのでしょうか?
親としては、焦る気持ちから
「なんとか元気になってほしい」「せめて少しでも前を向いてほしい」
そんな思いがあって、
「そろそろ何かしてみれば良いのにね」
「たまには気分転換に、外に出てみようよ」
「少し頑張ってみて」
などと、声をかけて提案してしまう。
それって、親子のあいだでよくある、ごく自然なことに思えますよね。
ところが、自己肯定感が低下しているひきこもりのこどもにとっては、親のこの“正しすぎる言葉”が、心に重くのしかかることがあります。
と言うのも、ひきこもりのこどもは
「自分が親を心配させている」「迷惑をかけている」
という罪悪感を常に感じているから・・・
そして、その状態で親から「頑張って」と言われると、
「まだ頑張りが足りないんだ」「やっぱり自分はダメだ」
と感じてしまうのです。
つまり、あなたの「励ましてあげよう」という優しさが、残念ながらわが子を追い詰める結果になってしまう可能性があるということ。
場合によっては、そんな悲しいすれ違いが、親子の間で起きてしまうかもしれないのです。
でも、これは“親の言葉かけ”が悪い訳ではありません。
自己肯定感を失ったひきこもりの子は、心のエネルギーが枯れてしまっていて、その言葉をまだ受け止めきれない状態にあるのです。
だから、そんな時こそ必要なのが、「何もしなくても、あなたは大切な存在」という親からのメッセージなのです。
この、親からの“存在そのものの全肯定”こそが、ひきこもりの本人の自己肯定感を少しずつ取り戻す第一歩になっていきます。
※ひきこもりの子の状態を蝶になる前のサナギにたとえて伝えている、あなたの発想の転換におススメの記事です(*^^*)
「何もしていないように見える時間」こそ、回復のスタートライン。それって親自身も同じ?

親としては、じれったくてたまらない思いをするのが、ひきこもりのわが子が「何もしていないように見える」時間。
でも、実はその裏で、ひきこもりの本人なりに、たくさんの思考や感情が動いているはずです。
たとえば・・・
・前日の母親の言葉を思い出して、自分を責めている
・SNSで、自分とは大きく違ってきている同級生達の投稿を見て、胸が痛くなる
・「何とかしなくちゃ、このままではダメ」と苦しんでいる
外からは、ただ遊んでばかりいて何も変わっていないように見えても、内側ではさまざまな“心の葛藤”と向き合う作業を、少しずつ進めているのです。
だからこそ、親が「何もしなくていい時間」を過ごすわが子の成長を信じてあげることが、ひきこもりの子の安心感に繋がります。
そのために親が心がけることは、『焦らず、待つ』こと。
これって実は、他人から見ると『親のくせに何もしていない』と思われてしまうリスクがありますね。
でも、ここで理解するべきことは、その状態って、まさに親自身が、わが子に向けている視線かも知れないということ。
私たち親が、ひきこもりの子を焦らず見守る境地に至るまでには、どれだけの苦しみや悲しみ、切なさ、怒り、憤り、無力感、自責のループなどを乗り越えてきたことか・・・
でも、周りの他者はそれら私たち親の葛藤を、全く知りませんね。
だから、何も考えずに好き勝手なことを言ってくるわけです。
これって、すごく残念なこと。
だからこれと同じことを、せめてあなただけでも、ひきこもりの子にやらないであげて欲しいと私は考えています。
それをわが子に示していくのが、「生きているだけでいい」と、あなたが、“そのままのわが子”を受け止められるようになること。
そして『焦らず、待つ』ことなのです。
※あなたが必死にわが子を受け入れようとしている“今”って、こどもと同じ“さなぎ”の状態かも!ぜひ、こちらの記事をどうぞ^^
【関連記事】ひきこもりという悩みとさなぎの共通点とは?
親が自分を責めないことが、ひきこもりの子の自己肯定感を守る

実は、ひきこもりの子の自己肯定感を育てるために大切なのは、こどものケアをしている親自身の自己肯定感を高めることです。
「どうして、あのときもっと優しくできなかったんだろう」
「いつも些細なことで、つい怒ってしまっていた」
「あの時、あんなことを言わなければ・・・」
私もそうでしたが、ひきこもりの子がいる親の多くが、このように過去の子育てを振り返っては、自分を責めています。
でも、その自分責めの気持ちを抱えたまま頑張りすぎちゃうと、親自身の心がすり減ってしまうことにもなりかねません。
さらに、自分を責めれば責めるほど苦しさが増し、こどもに“安心”を届ける余裕もなくなっていきますよね。
でもそれって、あなたの望む状態からかけ離れていく結果になっちゃいませんか?
だからこそ、気づいてほしいことがあります。
それは、あなたがこれまで何度も何度も、泣きじゃくりながらもわが子のことを思い続けてきたこと。
この事実は、何にも変えられない尊いことですね。
そこであなたが、自分を許し、穏やかに過ごすことが大切。
自分を責めることを手放し、少しでも「私はこれでいい」と思えるようになると、その穏やかさがわが子に伝わっていく。
すると、こどもも同じように「今の自分でも、いいのかもしれない」と、徐々にそう思えるようになっていくのです。
つまり、あなたが自分を責めずに生きられるようになることが、ひきこもりの子の自己肯定感を守るための、大切なポイントになるのです。
※ひきこもりの子の親が、「周りからは見えない努力」を必死にやっていることを伝えている、あなた自身を肯定するためのおススメの記事です(*^^*)
まとめ|親の「あり方」が、こどもの自己肯定感を育てる

いかがでしょうか?
今日は、「ひきこもりの子の自己肯定感を支える親の心|「生きているだけでいい」」というテーマでお伝えしてきました。
ひきこもりのこどもが、再び一歩を踏み出すとき、最初に必要なのは“行動”ではありません。
それは、『自分をそのままで受け入れてもらえている』という、自分の存在自体を認めてもらった感覚です。
つまり、小手先のテクニックではなく、親の関わり方。
「何もしていなくても、あなたはあなたでいい」
この言葉を、親が本心から感じられるようになるとき、こどもは少しずつ、自分の存在を受け入れ始めます。
そして、親が焦らず、こどもの“存在”そのものを受け止めることで、こどもは少しずつ「もう一度、何かを始めたい」と感じ始めるのです。
行動を促すよりも、まず「存在を認める」こと。
それが、ひきこもりのこどもの自己肯定感を回復させるいちばんの近道なのです。
焦らなくていい。今すぐ結果を求めなくていい。
あなたの「生きているだけでいい」というまなざしが、わが子の心に“安心”という居場所をつくっていくと信じてみましょう。
FAQ(よくある質問)
こどものひきこもりや自己肯定感の問題は、ケースバイケースで「正解のない」テーマです。
だからこそ、多くの親達が共通して抱える不安や疑問に、ここではお答えしています。
あなたの心を少しでも軽くするヒントになれば、うれしいです(*^^*)
【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)
『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)
「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、
不登校・ひきこもりのわが子に、
どう接していいか分からないあなたが、
こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、
たっぷりお伝えしている音声セミナーです。もし今、わが子とどう関わればいいか分からず、
「もう限界かも…」と感じているなら、
ぜひこちらの音声セミナーを聞いてみてくださいね。
あなたが1日も早く、今、抱えている悩みから解放されることを願っています。
いつでも私は、あなたを応援しています♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を書いた人

- チェンジングカウンセラー®
-
~ひきこもりという悩みや生き辛さをチャンスに変えてなりたい自分へと導いていく~
《40代、50代女性専門》チェンジングカウンセラー®の平井いずみです。
現在、鹿児島県在住。インターネットを中心に活動していますが、時々屋久島に出没します。
最新の投稿
 不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由
不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由 ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景
ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景 不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ
不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法
ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法
メルマガ登録音声セミナープレゼント『脱不登校・ひきこもり! 母子コミュニケーション術5選』
「女性としての役割」・「女らしさ」に囚われ、
「こうしなきゃ!」と自分を追い詰めて苦しんでいる40代以上のあなたへ
気持ちをラクにする、チェンジング・カウンセリングⓇメール講座(全9日間)
【登録特典】音声セミナープレゼント(24分34秒)
「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、
不登校・ひきこもりのわが子に、どう接していいか分からないあなたが、
こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、たっぷりお伝えしている音声セミナーです。
『脱不登校・ひきこもり!
母子コミュニケーション術5選』
この音声セミナーを聴き、9日間届くメール講座を毎日読み進めていくと、これまでの生きづらさの理由に気付き、自分の生き方や在り方を振り返るきっかけになること間違いなし!
すると、これからの未来が明るく見えて来る(*^^*)
あなたも自分の中に隠れているその視点に気付き、ひきこもりという悩みをチャンスに変えて、なりたい自分を目指していく方法を学びましょう。