ひきこもり息子が動き出せた理由|自己肯定感と自己有用感の合わせ技

こんにちは。
不登校・ひきこもりの母親専門『チェンジングカウンセラーⓇ』の平井いずみです。
「こどもが家から出なくなってしまった・・・」
「どう接したらいいのか分からない・・・」
これは、わが子の不登校やひきこもりで悩む親なら、誰もが抱える切実な思いですね。
私も、かつてはまさに同じ気持ちで悩み苦しんだ経験があります。
息子は高校1年の夏休み明けから体調が悪くなり、さみだれ登校から完全不登校。その後、休学を経て2年生の学年末で退学。
こうして所属が無くなった息子は、 “ひきこもり” という状態になっていったのです。
だけど、ある行動が息子の背中を押し、外の世界への一歩を踏み出すきっかけになりました。
そこで今日は、『ひきこもり息子が動き出せた理由|自己肯定感と自己有用感の合わせ技』というテーマで、「生きているだけでいい」と見守った先に生まれた一歩について、具体的にお伝えします。
あなたの心が少しでも軽くなりますように・・・
目次
ひきこもり脱出の第一歩は「自己肯定感」を取り戻すこと|心の回復が行動を生む

実はひきこもりになるということは、『今の自分ではだめ』と、自分にバツをつけて自己否定に陥っている状態ですね。
だからその自己否定感を上書きし、自己肯定感を育てていくことが、ひきこもりから抜け出すことに繋がっていきます。
では、自己肯定感とはいったいなんでしょうか。
それは、そのままの自分を認め
「自分は大切な存在」
「自分はかけがえのない存在」
だと思えること。
つまり・・・自分の良い部分だけでなく、悪い所・出来ない所までひっくるめて、そんな自分にOKが出せること。
実際、息子は自己肯定感を育てることで具体的な行動を起こすエネルギーが貯まり、不思議とひきこもりから抜け出したのです。
不登校・ひきこもりと自己肯定感の関連性について、内閣府の統計を基にお伝えしています。
→【関連記事】子どもの不登校・ひきこもりと自己肯定感の関連性
「生きているだけでいい」で育っていた息子の「自己肯定感」
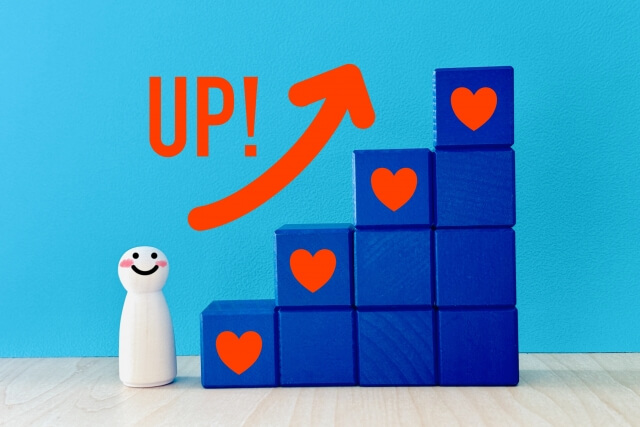
高校を完全不登校になってからは、ほぼひきこもり状態になって毎日ネットゲームに明け暮れていた息子。
その状態を、「悪いこと・ダメなこと」として、私たち親が無理やり矯正しようと躍起になっていた時期も、もちろんありました。
でも、“息子の命がけの抗議”をきっかけに、180度方針を転換。
たとえ24時間ゲームをしていようが、昼夜逆転になっていようが、それもすべて『彼の命を守る行動』と捉えました。
そして、私たち親は「見守る」という選択に切り替えたのです。
そこからすでに何年か経ち、息子は家の中ではとても元気になっていました。
家族ともよくしゃべるし、一緒にご飯も食べる。
昼夜逆転ではあったけれど、取り合えず手伝いを頼むとやってくれるし、暴言も暴力もない。
もちろん、まだ不安定な面はあって、息子にとって都合の悪い話題になると機嫌が悪くなり、部屋にひきこもることもありましたが。
それでも、息子が『ほぼ家から出ない』ということ以外は、本当に穏やかな凪のような生活。
息子の状態がここまで落ち着いたのには、それなりの年数が必要でした。
また、この状況に至るまでには、単に年数が経てばいいという訳ではなく、私たち親が息子を見守る前提としてのハードルを「生きているだけでいい」に、変えられたことが大きいと感じています。
そして、そのために私が手放したものは、息子に期待するあまり、彼を『親の価値観に合わせてコントロールしようとする』こと。
ここまで至るには、本当に紆余曲折いろいろありましたが、その中で私たち親子の関係性は良好になっていき、息子もどんどん元気を取り戻していったのです。
ただ、息子は家の中でたっぷりエネルギーを貯めてはいたものの、外の世界に向かうだけの力がなかったのも事実。
それは、当時はまだ、彼が次の一歩を踏み出すためのきっかけが無かったということなのです。
こどもに価値観を押し付けるとはどういうことかを、私の体験をもとに具体的に書いています。
→【関連記事】ひきこもりの子どもに親の価値観を押し付けていませんか?
きっかけは“自分で自分を守るための手段”である料理作り

でも、そのきっかけは、突然やってきました。
実は、1年足らずでしたが、息子が晩ご飯を作ってくれていた時期があって。
そしてこの晩ご飯作りこそが、思いがけず息子の自己肯定感という土台のもとで、彼がひきこもり脱出へと行動するきっかけになっていきました。
「晩ご飯作りがひきこもり脱出と、どうして繋がるの?」って、あなたはちょっと、戸惑っているかも知れませんね^^
でも、それは当然です。私自身、初めは全く想像していなかったですから。
実は、私たちが生きていくうえで、『ご飯を食べる』って、命に直結する絶対に欠かせないことですよね。そしてそのために必要なのは『料理を作れる』こと。
どんな状況になっても、自分でごはんを作ることさえ出来れば、何とか命を繋いでいけます。自立するためにも、不可欠ですね。
ということは、料理を作るのは、“自分で自分を守るための手段”だとも言えるのです。
でも、今の社会では『男は仕事、女は家庭』という考え方が根強く残っているため、男の子には料理を始めとして、初めから家事をさせていないケースが多くみられますね。
ご多分に漏れず、当時は私自身がこのような知識を持っていなかったため、こども達にあまり料理をさせてこなくて。
息子がひきこもりになってから、時々親子で一緒に共有体験を作りたくて、料理の手伝いを頼んだりはしていましたが、本格的に自分で献立から考えて作るのは、彼にとってはほぼ初めての体験。
だからこそ、“自分で自分を守るための手段”である晩ご飯作りをやり遂げたことは、息子の自信につながったのです。
息子と料理作りをした共有体験について書いています。
→【関連記事】ひきこもりの息子と笑顔の時間が作れた2つのこと
ひきこもり息子に「お母さんを助けて」と言えたらやって来たチャンス
それでは、ここから先は、どのように息子が晩ご飯作りを始めたか、そのプロセスについて具体的にお伝えしていきます。
息子のひきこもりに悩んでから、私は自分自身の生き方が大きく変わっていきました。
こども達の成長に合わせた仕事の選び方を止め、自分のやりたい仕事を見つけようと転職。そして何カ所かの勤務を経て、毎日ではないですが、出勤した日はフルタイムで働く仕事に就きました。
そのため帰宅が遅くなるので、私の出勤日の晩ご飯をお願いしようと思い付いたのです。でもこれには、私自身が、かなり考え方を見直さないといけないことが2つありました。
①私がひきこもりの息子に頼ること

まず1つ目は、私自身のこと。
『結婚したら、家事・育児は女性の仕事』という価値観をしっかり刷り込まれていた私。妻や母・嫁などの役割を、無理してでも、出来るだけ自分の力でやるべきだと思っていました。
そんな中、息子のことがあって、私は少しずつ考え方を柔軟にしていく練習をしていて。
とは言えまだ、ひきこもりの息子に晩ご飯作りを頼むというのは、結構ハードルが高い!
だって頑張れば自分で出来ることを、息子に頼ってしまうことになるのだから・・・これって、甘えなんじゃないか、という考え方も顔を出したりして。
それでも、役割に忙しくて自分のことを後回しにしがちな中で、意識してセルフケアのため週に何度か整体に通う生活を続けるために、「自分を大切にする時間を優先する練習」をしようと思えました。
そして、やっと「お母さんを助けて」と、息子に晩ご飯作りをお願いする許可を自分に出せたのです。
一生懸命まじめに「役割」を頑張っているあなた向けの記事です。
→【関連記事】家族の機嫌をとることに疲れている人の対処法
②ひきこもり息子の反応への不安や迷い・恐怖
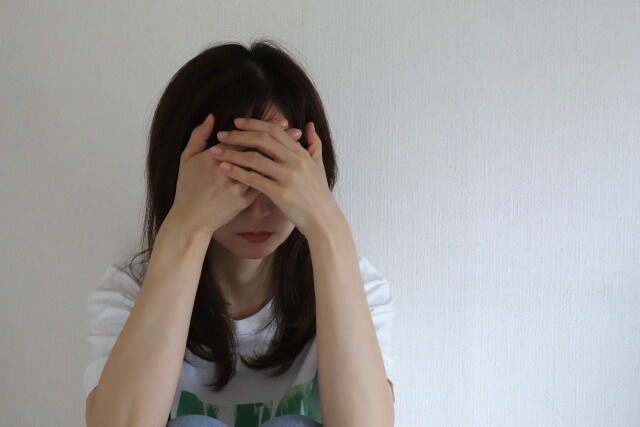
2つ目は、息子の反応が分からないこと。
「もしこの子が晩ご飯作りをプレッシャーに感じて、もっと心が折れてしまったらどうしよう・・・」という気持ちが、とても強かったです。
実は、私たち親の見守る姿勢が伝わり、本当に穏やかな生活を送れるようになっていたからこそ
「その生活を崩してしまう可能性のあることを今、やってしまってもいいのか」
という迷いや不安が私の中にはあり、その後息子がまた荒れた生活に戻ってしまうのではないか、という恐怖もありました。
でも、最終的に決断できたのは「伝えた結果は全部、私たち親子の経験になる」と思えたことです。
結局私は、不安や迷い・恐怖を抱えたままで、息子に「SOS」を出しました。
自分の言動で「一見穏やかな今の生活が崩れるかも知れない」と不安なあなたにオススメの記事です。
→【関連記事】『凪(なぎ)』のような日々が不安に感じるあなたへ
晩ご飯作りで育った「自己有用感」|家族の役に立てる体験が息子を動かした

その頃娘は、県外の大学に行っていて自宅にはいなかったので、夫と息子の3人で話をし、私は初めて「お母さんを助けてほしい。晩ご飯を作ってくれないかな?」と息子に頼んでみたのです。
すると、なんと!「出来なかったらいつでも止めていいなら、やってみてもいいよ」と、息子が引き受けてくれて(*^^*)
あっさり引き受けてくれたことに驚きながらも、すごく嬉しかったのを覚えています^^
①晩ご飯作りでひきこもり息子とした約束

実は、私たち夫婦は、晩ご飯作りに関して息子と約束をしていました。
・その日の晩ご飯を息子に任せる以上、何を出してもOK。
・昼夜逆転の不規則な生活だったため、時間が合わずに何も出来ていなくてもOK。
・何も準備していなかった時は、自分たちで家にあるものを何でも食べて済ませる。
・やってみて難しかったら、いつでもやめてOK。
息子が少しでも、晩ご飯作りへのハードルを下げられるようにこれらの約束を考えましたが、結果的には、これが本当に良かったと思います。
それと、もう1つ。夫と2人でこっそり決めたのは『どんなものでも、絶対に文句を言わず食べること』(笑)
そして私は、出勤の日は、置手紙と一緒にお金を置いて出かけるようになりました。
すると息子は、自分で決めたその日の献立に必要なものを買いに、バイクに乗ってスーパーへ。
こうして、それまではほぼ家にひきこもり状態だった息子が、スーパーに買い物に行けるようになったのです^^
②晩ご飯作りで起きたひきこもり息子の変化

こうして、週に3日~4日、息子が晩ご飯を作る生活がスタート!
私の中の、さまざまな葛藤を抱えながらも息子に頼ることを決め、「助けてほしい」と伝えたことがきっかけで、彼はどんどん変化していきました。
面白かったのが、レシート!息子はその日に貰ったレシートとお釣りを、必ずテーブルに置いていたので買ってきた品物が分かるんですね。
初めの頃は、律儀にも献立に必要な物ばかりがレシートに載っていて。
ところがしばらくすると、お菓子とか飲み物が加わってきたのです(笑)
それに気付いた時「今日はこれが欲しかったのね」と、私はすごく嬉しかったのを覚えています。
だって、彼のその日の気分や“好きなもの”が分かるから。
だけど、もちろん帰宅すると何も準備されてなくて、ぐっすり寝たままの時もありました。
それでもしばらくすると、昼間のうちに準備して「今から寝るから、レンジに準備してあるものを食べてね」などと、置手紙があることも。
息子は自分なりに生活のリズムを考えて、工夫出来るようになっていきました。
そして、初めは全く想像もしていなかったのですが、実はこの晩ご飯作りが、息子にとってはひきこもりから抜け出すための大きなチカラになっていたのです。
③ひきこもり息子が晩ご飯作りで手に入れた「自己有用感」
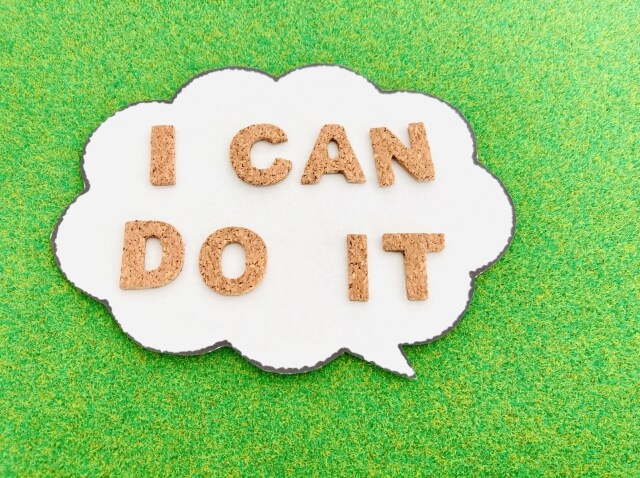
今振り返って思うことは、家族のために晩ご飯を作ることって、自分が家族の一員として役に立っていることを証明し、それを体感出来るという大きな意味があったということ。
献立を考え、買い物に行き、晩ご飯を作る。これを息子が本格的に自分の力だけでやったのは、もちろんこの時が初めてでした。
そして家族で一緒に晩ご飯を食べ、みんなが笑顔の食卓。
「生きていてくれるだけでOK」というところまで私たちがハードルを下げていた息子が、晩ご飯を作ってくれるのです^^
感動でしかありません☆彡
「おいしいよ」「ありがとう」「うれしいな」と、自然と息子に感謝していました。
こうやって、自分の力だけで晩ご飯を作りながら「達成感」を味わい、それを家族の喜んで貰えることで「自己有用感」が育まれていく。
やっていることは、ほんの些細な一歩だったかも知れない。
だけど、その一歩を積み重ねていくうちに、いつの間にか息子の中で、ひきこもり脱出への行動を起こせるだけの自信とエネルギーが、どんどん貯まっていったのです。
④晩ご飯作りからついにアルバイト開始へ

晩ご飯作りを開始して半年程経った頃、息子はゲーム仲間とのオフ会に行くと言って、1人で準備をして4泊5日の旅に出発!
そして、オフ会から無事帰宅。
その後しばらくすると、面接の準備を始め、コンビニでのバイトを開始。
こうして息子は、晴れて、晩ご飯づくりから卒業の日を迎えることができました。
そこで1年間バイトした後、専門学校に入学。無事、2年で卒業するとそのまま就職して自立した息子。
こうして、あれよあれよという間に、息子はひきこもりから抜出!
更に、料理をする経験を積んだことで、彼は就職後も会社の長期出張の時に、外食だけではなく時には自分でご飯を炊き、お弁当を詰めたりもしていて^^
このように息子は、少しずつ自分の世話を、自分で焼くことが出来るようになっていったのです。
息子が無表情で、蝋人形のようだった頃は「この子が、もう一度笑ってくれたらそれでいい」と、願うだけの毎日を過ごしたことすらあって(涙)
でも今思えば、“生きていてくれるだけでOK”と見守った日々が、息子の中に「自己肯定感」と「自己有用感」という2つの力を育てていたのだと思います。
もし今、あなたのお子さんが動けずに苦しんでいるとしても、焦らなくて大丈夫。
「生きているだけでいい」と見守るその姿勢が、きっとあなた達親子の“次の一歩”につながっていくはずだから☆彡
【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)
『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)
「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、
不登校・ひきこもりのわが子に、
どう接していいか分からないあなたが、
こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、
たっぷりお伝えしている音声セミナーです。
まとめ|自己肯定感と自己有用感の両輪でこどもは動き出す

いかがでしょうか?
今日は、「ひきこもり息子が動き出せた理由|自己肯定感と自己有用感の合わせ技」についてお伝えしてきました。
息子が外の世界へ出ることができたのは、“生きていてくれるだけでOK”という、私たちの見守りによって育った「自己肯定感」の土台があったからこそ。
そして、その上でエネルギーが貯まってきたら、家族の一員として何らかの活動をするステップに進む。
すると、“家族の役に立てた”という「自己有用感」が加わったことで、彼は『自分にもできることがある』と信じられるようになり、現実の行動に結びついたのです。
この二つは、まるで車の両輪のようなもの。
どちらか一方では動けなくても、両方がそろえば、たとえゆっくりでも前に進めます。
実際私も、息子に晩ご飯作りをお願いするときには、こんなにもミラクルな結果に繋がっていくとは考えてもいませんでした。
なんせ、不安や迷い・恐怖に囚われて、思いっきり悩んでいたくらいですから・・・
でも、どんなところにも、きっと、こうして突破口があるのだと思います。
だから、そういう視点を持つことで、もしかしたら何かが変わって行くかも知れませんね。
あなたのお子さんにも、きっとその力はすでにあるはず(*^_^*)
だからあなたも“生きているだけでいい”という優しいまなざしで、今日も見守ってあげてくださいね。
あなたにとっての突破口が、一日も早く見つかるように応援しています。
FAQ(よくある質問)
最後に、よくある“自己肯定感”と“自己有用感”についての質問への回答を、Q&A形式でまとめました。
あなたの心を少しでも軽くするヒントになれば、うれしいです(*^^*)
あなたが1日も早く、今の悩みから解放されることを願っています。
いつでも私は、あなたを応援しています♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
~あなたが、ひきこもりの息子さんのことで悩んでいるなら『チェンジング・カウンセリング®』がお役に立てると思います~
この記事を書いた人

- チェンジングカウンセラー®
-
~ひきこもりという悩みや生き辛さをチャンスに変えてなりたい自分へと導いていく~
《40代、50代女性専門》チェンジングカウンセラー®の平井いずみです。
現在、鹿児島県在住。インターネットを中心に活動していますが、時々屋久島に出没します。
最新の投稿
 不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由
不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由 ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景
ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景 不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ
不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法
ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法
メルマガ登録無料音声セミナープレゼント『不登校・ひきこもり! 母子コミュニケーション術5選』〜母親が整うと、関係は変わり始める〜
「女性としての役割」・「女らしさ」に囚われ、
「こうしなきゃ!」と自分を追い詰めて苦しんでいるあなたへ
気持ちをラクにする、チェンジング・カウンセリングⓇメール講座(全9日間)
【登録特典】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)
「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、
不登校・ひきこもりのわが子に、どう接していいか分からないあなたが、
こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、たっぷりお伝えしている音声セミナーです。
『不登校・ひきこもり!
母子コミュニケーション術5選』
この音声セミナーを聴き、9日間届くメール講座を自分のペースで読み進めてみてくださいね。
すると、これまでの生きづらさの理由に気づき、自分の生き方や在り方を振り返るきっかけが見つかるはずです。
子どもよりも、まずあなた自身の中に隠れている力に気付き、自分を整えながら、少しずつなりたい自分を目指してみませんか?

